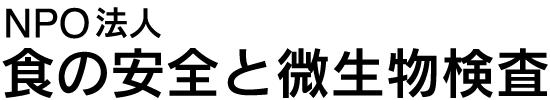今回の定期通信では、平成23年度講演会の聴講記録をご紹介いたします。
講演I-1:新たに判明した寄生虫による食中毒の詳細とその検査法―生鮮獣肉を共通食とする食中毒―(鎌田 洋一 先生)
講演I-2:新たに判明した寄生虫による食中毒の詳細とその検査法―生鮮魚肉を共通食とする食中毒―(大西 貴弘 先生)
講演Ⅱ:拡張型β-ラクタマーゼ産生菌の増加と食品衛生への影響(石井 良和 先生)
平成23年度講演会 講演Ⅰ-1
新たに判明した寄生虫による食中毒の詳細とその検査法
―生鮮獣肉を共通食とする食中毒―
鎌田 洋一
(国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 第三室長)
食中毒事例の共通食について細菌学的およびウイルス学的検査を行っても病原体が検出されない、検出されてもその数が少ない、あるいは症状その他と合致しない原因不明食中毒が平成14年くらいから増加しています。
共通食の一つに「馬肉」があります。馬肉を生食後、数時間から半日くらいで、嘔気,嘔吐,下痢,腹痛を起こし、時に悪寒,発熱,倦怠感,脱力の症状を呈します。通常は1日程度の病期ですが、消化器症状以外を呈すると数日の場合もあります。
獣医学領域では、喫食部分中に、住肉胞子虫のシストが寄生している場合があることが教科書レベルで記載されています。有症事例患者が喫食した馬肉を顕微鏡で調べると、幅0.5㎜、長さ7㎜程度の白色線虫様のシストが検出分離されました。寄生虫学的検査の結果、馬肉に寄生していたのは、Sarcocystis fayeriと同定されました。S.fayeriはイヌを終宿主、ウマを中間宿主とし、ウマ筋肉中でシストとして存在します。シストの中には、イヌ腸管上皮細胞に感染できるブラディゾイトが多数含まれており、S.fayeriはヒトには寄生しないとされています。
統計疫学解析を行いますと、馬肉について高いオッズ比が得られている事例があります。国内の一部地域で有症苦情事例として報告があります。通信販売や冷蔵流通の手段が発達しており、馬肉による食中毒事例は、今後、全国から報告が出てくることも予想されます
S.fayeriを含んだ馬肉のホモジネートをウサギ腸管ループ内に投与したところ、顕著な液体貯留が観察されました。同シスト、およびブラディゾイトにも液体貯留活性があり、寄生馬肉およびS.fayeriの腸管病原性が示されました。しかし、ペプシン処理をしたS.fayeriを投与した場合、液体貯留は観察されませんでした。馬肉による食中毒は、S.fayeriが持つ、タンパク質分解酵素に感受性のある物質が原因であることが示唆されます。
馬体のどの部分にS.fayeriシストが寄生するか検査したところ、喫食部分の多くにシストが見られました。しかし、内臓や脂肪組織ではシストは検出されませんでした。ウマの生産地にシスト保有率の違いがあるか検討したところ、外国産馬26頭すべてにシストの寄生が見られました。国産馬においては、7頭中3頭にシストが検出されました。
有症事例馬肉と、一般流通馬肉中のS.fayeri寄生率を比較したところ、事例馬肉中には50倍以上のシストが存在しました。馬肉には、少数ではありますがS.fayeriの寄生があること、そして発症するのは、偶然に大量のシストの寄生がある部分を喫食したからだと考えることができるでしょう。
Sarcocystisの危害性を制御する方法として、馬肉の冷凍処理を試みました。-20℃では48時間、-30℃では18時間以上保持すると、ブラディゾイトが死滅しました。冷蔵馬肉中のS.fayeriのシストは、人工胃液処理に抵抗性を示します。冷凍処理を行ったシスト含有馬肉では、人工胃液処理でシストの消失が起こりました。これらの結果は、冷凍工程を組み入れることで、馬肉の安全性を担保できる可能性を示しています。
ウシに寄生するS.cruziは、ウサギ致死活性を持つタンパク質性の毒素をもつという報告があります。S.fayeriのシストを凍結融解後、タンパク質抽出物を得、ゲルろ過法でタンパク質を分画しました。分子量が15KDa付近のタンパク質分画が、ウサギに下痢と致死を誘導しました。古い研究ではありますが、Trypanosoma gambienseが産生する毒素が知られており、これは、ラットに低血糖を誘発します。またこの毒素をマウスに静脈内注射すると、激しい痙攣、麻痺症状、運動機能障害、呼吸困難、死亡を誘発したとする報告があります。「寄生虫毒素による食中毒」という概念もあってよいと考えます。
馬肉中のSarcocystis検査法としては、実体顕微鏡によるシストの確認、採取があります。これは、シストを直接証明することができますが、シストと脂肪組織との鑑別に経験が必要です。その他の方法としては、トリプシン消化法があります。これは、馬肉を粥状にトリプシン消化し、沈殿物中のブラディゾイトを鏡検するものです。また、組織切片鏡検法という検査法もあり、馬肉のHE染色標本を作製し、1×1cm中のシストを顕微鏡下で計数する方法です。このとき、シストは塊としてヘマトキシリンで強染されます。最近では、PCR法が開発されています。なかでも定量リアルタイムPCR法は、八木田健司博士(感染研)が開発中で、高感度、迅速かつ定量性のよい方法になっており、暫時公開される予定です。
馬肉を共通食とする食中毒の原因として、住肉胞子虫Sarcocystis fayeriがあげられ、シストを構成するタンパク質に毒性があると予想されています。虫体の検査法もほぼ完成しています。馬肉における住肉胞子虫の危害性は、馬肉を冷凍処理することにより制御が可能です。今後事例の解析が進み、迅速スクリーニング法等が発展すれば、冷凍処理をしなくとも安全な馬肉を提供できる可能性もあると思われます。
平成22年度 講演会 講演Ⅰ-2
新たに判明した寄生虫による食中毒の詳細とその検査法
―生鮮魚肉を共通食とする食中毒―
大西 貴弘
(国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 第四室長)
魚肉は、高たんぱくでミネラルや必須脂肪酸など非常に栄養成分に富んだ食品です。そのため世界中でその消費が進んでおり、一方、世界中で魚肉の生食による食中毒事例が発生しています。
日本では平成15年頃より生鮮魚肉の生食に伴う新しい食中毒が増加し、今では年間100件を超える事例が報告されるようになってきました。この食中毒は一過性の下痢や嘔吐をおもな症状とし、潜伏期は2~3時間から16時間程度と非常に短く、喫食残品から既存の食中毒細菌やウイルス、化学物質が検出されないことが大きな特徴となっています。
食中毒患者の共通食にはヒラメが含まれていることが多いことから、ヒラメに含まれるDNAの網羅的解析を行い、病原体候補検索を行った結果、本食中毒の喫食残品のヒラメにはKudoa属に属する粘液胞子虫のDNAが含まれていることが明らかになりました。
Kudoa属はミミズやゴカイを終宿主とする寄生虫で、4極の胞子を持つものはヒラメの筋肉を融解させる特徴があります。また、6極の胞子を持つものが発見され、新種のKudoa septempunctataの関与が疑われ、これがヒトに食中毒を引き起こすのではないかと疑われました。
このKudoa属の胞子を乳のみマウスに投与しKudoa属胞子の下痢原性を確認したところ、下痢を引き起こすことが確認できました。また、スンクスを用いた嘔吐モデルでは、Kudoa属胞子は嘔吐を引き起こしました。いずれの場合も、数時間後には症状は解消されたことから、予後はよいと思われます。さらに、ヒトの腸管上皮モデル細胞(Caco-2細胞)にKudoa属胞子を投与すると、腸管上皮細胞の物質透過性が亢進しました。Kudoa非含有ヒラメホモジネイトで同様の実験を行った場合、症状は認められなかったことより、Kudoa属の粘液胞子虫、特にK. septempunctataが本食中毒の原因微生物の一つであることが明らかとなりました。
現在Kudoa属の失活法としては、冷蔵(4~10℃)で一週間保存、または-80℃で2時間以上保存、あるいは-20℃で4時間以上保存が有効であるとされています。また、75℃で5分の加熱も有効です。冷蔵(4~10℃)で経過日数とともに毒性が減少することから、これらが現在有効なクドアの失活法と考えられています。
Kudoa属の検査法は、①DNAを用いた定量リアルタイムPCR法、②ヒラメの筋肉を細切し顕微鏡所見でのKudoa胞子の観察、③培養細胞に対する毒性の確認が確立されています。養殖場でのモニタリングのための検査法としては、①ヒラメに寄生する3種類のクドアを区別できる28S rDNA PCR、②鰓蓋裏の筋肉を用いた簡易診断法があります。 予防策としては、養殖現場に稚魚を導入する段階で汚染稚魚を排除すること、養殖時の飼育環境からの汚染を防止することが重要であると思われます。
生鮮魚類に冷凍や冷蔵処理を行うことは商品価値を下げることになります。したがって、こうした食中毒の発生を減らすためには、魚にKudoa属を最初から寄生させない対策が必要となります。Kudoa属は寄生している魚から他の魚への水平伝播は起きないとされていることから、こうした対策が有効であると考えられます。
今後、ヒラメ養殖現場に稚魚を導入する段階で汚染稚魚を排除し、出荷前の汚染のモニタリング体制などを構築するとともに、流通・加工段階における対策を構築していくことが、本食中毒事例を減少させるために必要であると思われます。
平成22年度 講演会 講演Ⅱ
拡張型β-ラクタマーゼ産生菌の増加と食品衛生への影響
石井 良和
(東邦大学医学部微生物・感染症学講座 講師)
基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生菌(Extend-spectrum β-lactamase:ESBL)は、院内感染の起因菌として医療の現場で問題視されてきました。この耐性菌は、β-ラクタム系薬(ペニシリン系、セフェム系薬など)の基本構造であるβ-ラクタム環の加水分解酵素であるβ-ラクタマーゼを産生して耐性を付与しますが、その遺伝子は菌種を越えて伝播します。
これまでは、日本と欧米で検出されるESBLの種類や産生菌種は異なっていました。すなわち、欧米ではTEM型やSHV型のESBLを産生する肺炎桿菌の分離頻度が高く、日本ではCTX-M型のESBLを産生する大腸菌の分離頻度が高いという特徴がありました。しかし、最近は欧米でもCTX-M型のESBL産生大腸菌が分離される頻度が高くなっています。これはヒトやモノの流通が拡大するが耐性菌の世界的拡散に影響していると考えられています。
インドやパキスタンが発生源と見られる「NDM-1」と呼ばれる新種のβ-ラクタマーゼを産生する耐性菌による感染が、2010年9月栃木県で報告されました。この患者は南アジアへの渡航歴がありました。2010年10月には2例目の感染が報告されました。この患者は埼玉県内の医療機関に入院していた90歳代女性で、近年海外への渡航歴はなかったそうです。さらに2011年1月には3例目が報告されました。この患者も埼玉県内の医療機関に入院していた80歳代女性で、海外渡航歴はなかったそうです。これらの事実は、はじめ外国から侵入してきた耐性因子である「NDM-1」が日本国内において市中に広がっている可能性を示唆しているものと考えられます。
ESBLの分離頻度は年々増加していますが、その過半が外来症例です。これまで耐性菌は病院内で伝播すると考えられてきましたが、病院の受診歴や抗菌薬の投与歴を有さない外来患者も見られ、これまで常識とされていた院内における耐性菌の伝播経路とは別の経路があることが推定されました。
近年、欧州を中心に食品や飲料水を汚染するESBL産生菌についての検討が行われています。その結果、鶏肉から検出されるESBLとヒト由来のESBLに関連性が見られたとの報告があります。
これを受けて、2008年から演者らは、ESBL産生大腸菌について、患者由来株、健常人由来株、鶏肉及び鶏糞便由来株の比較検討を実施しました。その結果、①ESBL産生大腸菌は鶏からもヒトからも検出されること、②市販されている鶏肉からも高率にESBL産生大腸菌が検出されること、③ヒト由来株がST131&CTX-M-9産生株であり、鶏由来株はCTX-M-2産生株であったことから、両者の間には直接の関係は認められないことなどが明らかになりました。ESBL産生菌の増加には鶏肉を介さない別の経路がある可能性が高いと思われますが、現時点では明らかではありません。
ESBL産生菌はその耐性情報を染色体以外の遺伝子(プラスミド)などを介して伝達することが知られています。ヒト由来株のST131産生大腸菌は、フルオキノロン系薬に耐性を示し、かつ尿路系への接着因子を保有する菌株が多いことから、尿路感染症の原因菌となり易いと考えられます。このタイプの大腸菌がESBLの中でも強力なCTX-M-15を獲得すると、フルオキノロン系薬だけでなく、カルバペネム系薬を除くほぼ全てのβ-ラクタム系薬に耐性を示すようになるため、その動向には今後十分な注意を払わねばなりません。
これまで、治療に用いる抗菌薬の使用量の増加が耐性菌を誘導すると考えられてきました。しかし、ヒトの感染症治療にあまり使用されない抗菌薬が大量に使用される農畜水産分野が耐性菌の増加に及ぼすインパクトを耐性遺伝子が菌種を超えて伝播する仕組みとともに解明する必要があると考えられるようになっています。