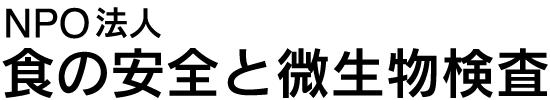定期通信 第37号では、本協議会の理事である貞升 健志 先生による「食品微生物分野における遺伝子検査技術の進歩」と題する書下ろしです。様々な検査手法が紹介されていますが、その可能性と解決すべき課題の多さを知ることができます。
是非、ご覧ください。
食品微生物分野における遺伝子検査技術の進歩
貞升 健志 (特定非営利活動法人食の安全を確保するための微生物検査協議会 理事)
微生物分野における遺伝子学的手法は、キャリー・バンクス・マリス(Kary B.Mullis)がPCR(polymerase chain
reaction)法で1993年に「ノーベル化学賞」を受賞して以降、急速に進歩し広がった。それまでは抽出したDNAを制限酵素で切断後、電気泳動で確認するくらいが精一杯で、量が少ない遺伝子配列を検出するには放射性同位元素で標識したプローブを使用するしかなく、食品の微生物検査での利用は夢のまた夢であった。
幸いにして、1990年前後には我々もPCR法を研究用に使用し始め、自分自身が設計した合成プライマーで標的遺伝子が増幅できることに興奮したことを思い出す。PCR法は微生物検査において劇的な変化を引き起こし、今まで培養できなかったウイルスの検出、細菌の薬剤耐性遺伝子や毒素遺伝子を短時間で検出できるようになった。
このように、微生物分野における遺伝子検査の技術的進歩は「検出」と「比較」の面で顕著である。今回、遺伝子の増幅原理、検出感度の向上、遺伝子配列の解析の側面から、食品微生物分野における遺伝子検査の進歩と今後の方向性について考えてみたい。
1. 様々な原理の遺伝子増幅法
PCR法以外にも様々な核酸増幅法が開発されており、LAMP法、SDA法、リアルタイムPCR法のようにDNAを増幅する方法ばかりでなく、NASBA法、TRC法、TMA法のようなRNAを増幅する方法もある。このような原理を用いたキット・機器は各企業により実用化され、我々ユーザーに使いやすいようにパッケージとして販売されている。
販売されたキットはしっかりと品質、精度が保証されている反面、専用の装置を購入しなければならないことが多い。そのため、キットの感度を比較するにはまず機器からということが多く、検査キットの比較もなかなか難しい時代となっている。
2. 「検出すること」・・・ノロウイルスを例に
日本において患者数が最も多い食中毒の原因物質であるノロウイルスは、遺伝子型の同定ばかりでなく糞便中のウイルス量まで測定可能である。かつては小型球形ウイルス(Small Round Structured Virus:SRSV)として知られ、1980年代には検査法として電子顕微鏡観察しかできなかった。
1990 年にクローニングが行われ全塩基配列が明らかにされると、逆転写酵素によりDNAにした上でPCR法を行う逆転写PCR 法( Reverse transcription-polymerase chain
reaction:RT–PCR)が検査に用いられるようになった。1997 年に旧厚生省は食中毒病因物質にSRSV を加え、2002 年に国際ウイルス命名委員会はこれをノロウイルスと命名した。2003
年、厚生労働省は検査法の見直しを行い,リアルタイムPCR 法を標準検査法とした。
2017年6月には大量調理施設衛生管理マニュアルが改正され、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めることとしている。その際、概ね糞便1g当たり105オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましいとされている。
現在、ノロウイルスは特殊な場合を除き、培養することが未だ困難であるが、ノロウイルス遺伝子の「検出」は定量できる域まで到達している。ノロウイルス検出における歴史を例に挙げたが、腸管出血性大腸菌のVT遺伝子検出法においてもリアルタイムPCR法等が厚生労働省通知の中に記載されており、「検出する」意味でのPCR法はほぼGoalに達した感がある。
3. 「比較すること」・・・細菌分野での遺伝子型別利用法を例に
微生物の検査を実施する上で、相同性を調べる作業は重要である。ある施設で細菌性の食中毒の発生があり、患者および食品から同様の菌が分離されたとする。患者および食品由来の細菌が同じか否か(=相同性)を調べることは、食中毒事件の解決のための重要な作業である。そのような場合、パルスフィールドゲル電気泳動(pulsed-field gel electrophoresis、PFGE)法が従来から用いられてきた。
PFGE法は1980年代に報告されたフラグメント解析法で、培地で増殖させた菌のDNAを制限酵素で切断し、DNA断片のパターンをゲル電気泳動でみる方法である。この方法はあらゆる菌について適用可能である反面、比較対象となる菌が同時にないと比較が困難である。感染症法により菌の搬送に規定がある現在では、菌の種類にもよるが授受が容易ではない場合がある。
菌の授受を要さない方法として、2012年ころからマルチプレックスPCR法を用いた型別法が実施されるようになった。ある複数の遺伝子の存在をマルチプレックスPCR法により同時に検出し、増幅された遺伝子が存在するか否かを数値に置き換えてナンバリングする方法であり、腸管出血性大腸菌O157ではIS-printing 、MRSAではPOT法が知られている。
また、MLST (multi locus sequence
typing)法は1998年に開発された方法で、すべての菌株に必ず存在し、わずかに塩基置換がみられるハウスキーピング遺伝子を解析後、専用のWebサイトにデータを入力することで型別を行うことができる。
さらに、2014年ころから分子型別として反復配列多型解析法(multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis; MLVA)が多様な病原細菌を対象に開発された。細菌ゲノムには単一配列が連なって(タンデム)リピートする領域(繰り返し配列)が複数存在し、かつ比較的頻繁にリピート数が変化することが知られており、これら株ごとのリピート数の違いを基に菌株を型別する方法である。
基本的な検査手技は、各領域をPCR法で増幅し、アガロースゲル電気泳動で増幅産物の分子量を確認することにより、またはシークエンサーを用いて増幅産物の大きさを測ることで各部位のリピート数を同定する。腸管出血性大腸菌では17か所のリピートする遺伝子座が知られており、各々のリピート数を並べた数値で菌株を分類する。
菌の遺伝子型を数値で表すことは、実際に菌の授受をすることなく、菌の比較ができる点で優れている反面、検査実施者の手技の統一化、精度管理が前提条件として必要である。IS-printing
やPOT法については既にキット化がなされているが、使用できる菌が限定されており適用範囲が広いとはいえない。
2018年2 月8 日に厚生労働省より、都道府県に向けて、腸管出血性大腸菌のMLVA法による検査体制の確保、整備についての通知がなされた。腸管出血性大腸菌は感染症法の3類感染症(全数報告疾患)で全国約4,000例/年の患者報告があるが、MLVA法による型別情報を広域で共有することで原因究明を迅速化し、事件の拡大を防ぐのが目的である。
MLVA法を都道府県の検査で安定的に実施していくためには、試薬のキット化、検査手技の統一化を図るための精度管理の実施、地域別の型別情報のデータベース化等のさらなる進化が望まれる。
4. 「検出も比較もする」・・・次世代シーケンサー利用法
近年、さらに新たな遺伝子解析法が利用されてきている。次世代シーケンシンサー(NGS)である。NGSは数千から数百万ものDNA分子を同時に配列決定可能な強力な基盤技術で、近年、病原体検査にも応用されつつある。
ウイルス遺伝子は1万塩基程度の大きさであるが、大腸菌では4.64Mb(4.6×106 bp)のゲノムサイズがある。ゲノム情報があればMLVA法やMLST法の結果も判明し、毒素遺伝子の有無のみでなく、他のすべての遺伝子の有無や遺伝子全体のどの部分にそれらの遺伝子が配置されているのかをも知ることができる。
例えば腸管出血性大腸菌の場合、どのようなベロ毒素(VT)遺伝子が遺伝子全体のどこに組み込まれているのかを知ることができるのである。また、不明疾患でいろいろな病原体の遺伝子検査を実施したが全て陰性となり病原体が分からない場合、患者の検体からNGSを用いた網羅的ゲノム解析を行うことにより病原体をあぶり出すことも期待される。
一方で、特に細菌では取得される情報量がメガバイト(Mb)からギガバイト(Gb)へと著しく大きくなり、解析法もまだまだしっかりと固定化、マニュアル化されたものがない。例えば、従来法のPFGEでは同じ型と判定されても、NGS解析では相同性の面で異なる結果が出てくることも想定される。
進化学的にどこまでの差を同じ起源と捉え、どこから異なる起源と定義するか等が今後の課題といえる。また、ゲノムサイズが大きくなると、今までのように簡単にゲノムの比較ができるソフトは存在せず、様々なフリーソフト等を組み合わせる等、解析手法も切磋琢磨されている現状がある。
食品微生物の遺伝子解析について知っているつもりであったが、まだまだ奥は深くGoalは見えない。取得したゲノム情報の大量の波に埋もれないように、我々も努力をして利用法を学なければならない。
ノロウイルスや腸管出血性大腸菌はタンパク質からできており、タンパク質は全て遺伝子によりコードされている。従って、遺伝子を調べればタンパク質が解る、微生物が解るという論理は一見成立する。しかしながら、見かけ上同じ遺伝子型の病原体でもヒトへの病原性が異なる場合は多々存在しており、必ずしも我々の体の中で同じようにタンパク質として影響しているかどうかは定かではない。遺伝子が研究されればされるほど、改めてタンパク質についての理解や研究の推進が必要になっていくものと思っている。